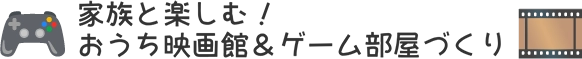ゲームに集中している姿を見ると、「つい熱中しすぎじゃないか」と心配になることもあるかもしれません。私自身、週末には家族でマリオカートやスプラトゥーンを楽しんでいます。映画もゲームも大好きな家族にとって、「どれだけ楽しく、けれどだらけすぎずに過ごせるか」は、ずっと試行錯誤のテーマです。
ゲームは“共有する体験”になる
ゲームと聞くと、孤独に黙々と画面に向かうイメージを持たれがちですが、我が家ではまったく逆です。週末になると「今日はどのゲームにする?」と息子に聞かれます。家族みんなでコントローラーを持って大笑いする時間は、仕事で疲れた私にとっても癒しの時間。息子の成長を間近で感じられる貴重なひとときでもあります。
このような経験を通して、「ゲーム=悪いもの」と決めつけず、まずは“共有できる体験”として向き合ってみることの大切さを実感しました。
わが家ルールは“話し合って決める”が基本
ある日、息子が寝る直前までゲームをしていて、翌朝寝坊してしまいました。それをきっかけに、家族でゲームのルールについて話し合うことに。驚いたのは、息子が思ったよりも「自分でどうしたらいいか」を考えていたのです。自分なりに「〇時までにやめた方がいいかな」と話してくれました。
この体験から学んだのは、ルールは“押し付けるもの”ではなく、“一緒に作るもの”だということ。納得感があると、子ども自身もルールを意識するようになります。
守れる仕組みにするために工夫したこと
うちでは、ゲーム時間を「平日は1日1時間まで」「週末は2時間まで」とざっくり決めています。守れた日は、夕食のときにさりげなく褒めたり、「今日は早めに終わったね」と声をかけるようにしました。何気ない一言でも、子どもはちゃんと受け取っているように感じます。
反対に、約束を守れなかったときも、叱るより先に「何があった?」と聞くようにしています。ルールは堅苦しいものではなく、“楽しく続けるための仕掛け”と考えると、親も子も気がラクになります。
親も少しだけ“プレイヤー”になる
ゲームの内容を理解していないと、注意するタイミングもズレてしまうことがあります。実際、私も以前は「そんなに夢中にならなくても…」と思っていたのですが、いざ自分でやってみると、思ったより頭を使うし、息子との会話も増えました。
子どもが「このステージ難しいんだよ!」と楽しそうに話してくる姿を見ると、それを聞いてあげられることが嬉しくなります。少しでもプレイヤーとして参加することで、子どもの世界に自然に入り込める気がします。
ゲームをきっかけに、会話が生まれる暮らし
わが家では、ゲームを通して、子どもとの関係がより深まったと感じています。もちろん、悩むこともありますし、うまくいかない日もあります。ただ、ルールがあるからこそ、家族で過ごすただ、ルールがあるからこそ、家族で過ごす時間に“けじめ”が生まれ、ゲームの楽しさもより引き立つようになりました。
“やめる時間を守れた”、“今日は協力プレイがうまくいった”――そんな日常の積み重ねが、大切だと思います。
おわりに
ゲームは、家庭内の「壁」ではなく、「橋」にもなり得ます。無理に制限するよりも、親子で一緒にルールを作り、楽しみ、時には見直していく。それが自然な形で、子どもの成長や自立を後押ししてくれると、私は実感しています。
ゲームとの付き合い方は、家族によっていろいろです。でも、どんな家庭でも「一緒に過ごす時間を大切にする」という思いがあれば、それが何よりの答えになるのではないでしょうか。